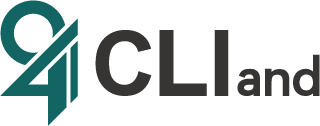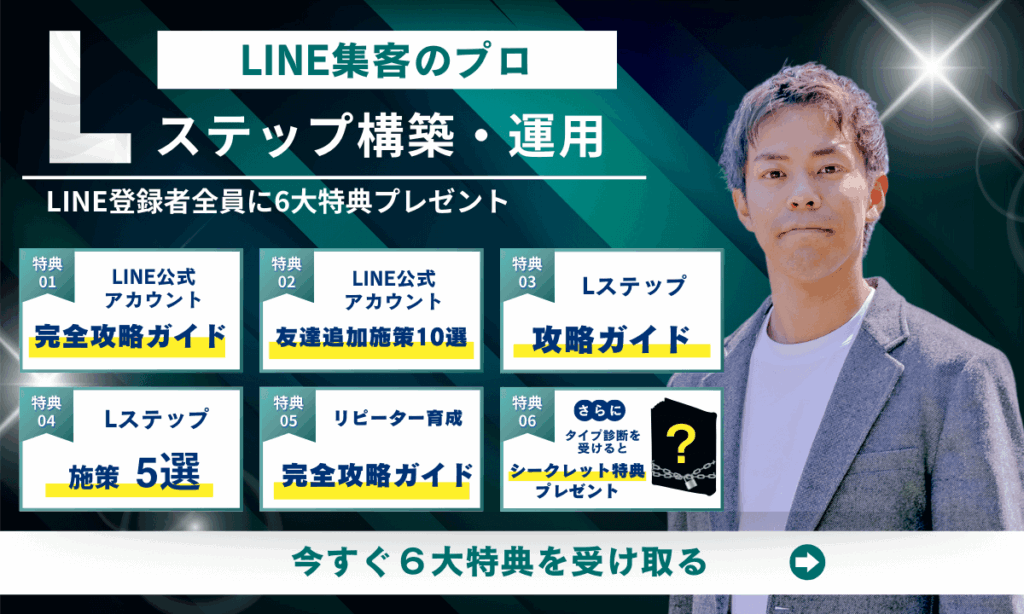Webサイト制作は重要な業務ですが、以下のような不安を抱えている方も少なくありません。
「Webサイトを作りたいけど、何から始めればいいの?」
「制作会社に依頼するにも、流れがわからない…」
そこで今回は、Webサイトを制作する流れを解説します。
事前に決めておくべき項目や設計からリリースまでの制作ステップ、公開後の運用方法に加え、スムーズに進めるための準備ポイントも解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
Webサイトを制作する流れとは?事前に決めておくべきこと

まず、Webサイトを制作する流れと事前に決めておくべきことを5つ紹介します。
- Webサイトを制作する目的を決める
- ゴールを決める
- 具体的なターゲットを決める
- 制作予算を決める
- 余裕のあるスケジュールを設定する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
Webサイトを制作する目的を決める
Webサイトは売上拡大や顧客獲得などの目的を達成する手段であり、作ること自体が目的になってはいけません。
問い合わせ数を増やす・ブランドの信頼性を高めるなど、何を目指すかを明確にすれば、サイトの構成や必要な機能・ユーザー像も自然と定まります。目的がはっきりしていれば、制作会社への依頼内容も具体化し、戦略的な提案や効果的な設計が期待できます。
Web制作の方向性が決まっていれば、制作プロセス全体がスムーズに進むでしょう。
ゴールを決める
目的を設定したら、達成の目安となる数値ゴールを決めましょう。
「問い合わせ数を月30件から100件に増やす」といったKPIを定めておけば、成果の評価がしやすくなります。制作会社との認識ズレも防げるため、実現可能なプランの共有にも役立つはずです。
具体的な数値があれば、公開後の分析や改善にも活かしやすく、目標に対する進捗を見える化できます。
具体的なターゲットを決める
目的とゴールが定まったら、次はサイトを見る人の人物像を明確にしましょう。
単に「20代女性」といった属性ではなく、年齢・職業・悩み・価値観などを反映したペルソナを設定するのが欠かせません。詳細なユーザー像を作れば、コンテンツやデザイン、導線設計に一貫性が生まれます。
また、関係者間で共通認識が持てるため、プロジェクトが迷走しにくくなるでしょう。
制作予算を決める
制作費はサイトの規模や構成によって大きく変動します。
あらかじめ予算の上限を決め、制作会社に伝えておけば、費用対効果の高い提案を受けやすくなるでしょう。初期制作費だけでなく、サーバー・ドメイン費用、保守費用といった運用コストも含めた予算計画を立てるのが望ましいです。
余裕のあるスケジュールを設定する
サイト制作は、中規模でも2〜3ヶ月程度、大規模なら半年以上かかる場合もあります。
短期間で進めようとすると、企画が曖昧になったり、デザインや開発で認識のズレが生じるリスクがあるでしょう。テスト期間が確保できないと、公開後に不具合が発生する恐れもあります。
そのため、公開日から逆算し、各工程に余裕を持たせたスケジュールを組むことが大切です。
【設計~リリースまで】Webサイト制作の基本的な流れ

ここでは、Webサイト制作の基本的な流れを9ステップで解説します。
- STEP1|競合調査とコンセプト設計
- STEP2|要件定義
- STEP3|サイト全体の構成を決める
- STEP4|ワイヤーフレームの作成
- STEP5|デザイン作成
- STEP6|コーディング
- STEP7|システム開発
- STEP8|テストの実施
- STEP9|リリース
それぞれ詳しく見ていきましょう。
STEP1|競合調査とコンセプト設計
まず取り組むべきは、誰に何を伝えるサイトにするかをはっきりさせることです。
そのために、ターゲットや目的を整理し、競合サイトを調べて差別化のヒントを探すのが出発点になります。自社の強みを言語化できれば、どんな方向性で伝えるべきかも見えてくるでしょう。
「情報提供重視なのか、問い合わせ獲得が目的なのか」など、目的に合った設計の軸を定めることが大切です。分析した内容をもとに、サイト全体を通じて届けたいメッセージを明文化すれば、関係者との認識も揃いやすくなるでしょう。
初期段階で方向性を固めておくと、後の作業も無駄が出にくくなります。
STEP2|要件定義
Webサイトに必要な機能や仕様を先に決めておくことは、とても重要です。
具体的には、フォーム機能の有無・使用するCMSやサーバー・保守対応の範囲など、技術面や運用面の条件を整理しておけば、後からのズレや手戻りを防げます。
また、情報の正確さや安全性を保つために、セキュリティの方針や品質基準もこの段階で決めておくべきです。認識違いを防ぐには、口頭の確認だけでなく、ドキュメントにして共有するのも忘れないでください。
関係者全員が「何を作るのか」「どこまで対応するのか」を理解していれば、サイト制作がスムーズに進みやすくなるでしょう。
STEP3|サイト全体の構成を決める
次は、必要なページとそのつながりを整理するステップです。
構成を図でまとめた「サイトマップ」があると、ユーザーの導線やページの優先度が一目でわかります。迷わせない導線にするには、情報の階層を深くしすぎないことがポイントです。
どのページで何を伝えるかが決まれば、自然とメニューやリンクの設計にも整合性が生まれます。あわせて、検索エンジンからの評価も意識し、カテゴリごとにキーワードを振り分けるのも検討しましょう。
わかりやすさと検索性の両方を意識して設計すれば、使いやすさにもつながります。
STEP4|ワイヤーフレームの作成
ページごとの設計図にあたるのがワイヤーフレームです。
構成が決まったら、各ページでどの情報をどの位置に配置するかを視覚的に整理します。レイアウト・見出しの構成・ボタンの配置・情報量のバランスなどを決めておくと、次のデザイン工程がスムーズになるでしょう。
線と枠だけでシンプルに構成されているため、誰が見ても構成を理解しやすいのが特長です。また、チーム内で認識を揃えるために、CTAの位置や意図、動線の流れについても補足を入れておくと安心です。
ワイヤーフレームが曖昧だと制作途中で修正が発生しやすくなるため、できるだけ具体的に作成しておくと後工程の手間も減らせるでしょう。
STEP5|デザイン作成
次の工程では、ワイヤーフレームをもとにWebサイトの見た目を整える作業に入ります。
見た目の美しさだけでなく、情報の伝わりやすさや使いやすさを意識しましょう。コンセプトやターゲットに合ったカラー・フォント・画像などを選び・トーン&マナーを統一します。
たとえば、信頼感を与えたい場合は落ち着いた配色、行動を促したい場合は視認性の高いボタンなど、目的に応じた工夫が求められます。デザイン案は初期段階で細かく確認し、見た目だけでなくUXの観点からも調整できるようにしておくと安心です。
この段階での認識違いは、後の修正コストにつながる場合が多いため、早めにすり合わせておくのがポイントです。
STEP6|コーディング
デザインが固まったら、Webサイトとして実際に動かせるようにコーディングします。
HTML・CSS・JavaScriptなどを使ってページを構築し、ブラウザで正しく表示される状態をつくる工程です。表面的な再現だけでなく、表示速度やSEO対策・スマートフォン対応なども意識しながら実装を進めましょう。
この作業は制作会社が担当する場合が多いため、発注側は指示書や原稿の準備、確認対応などで協力する場面が出てきます。途中でレイアウト修正や文言変更があった場合は、できるだけ早めに伝えると対応もスムーズです。
細かな調整が多いフェーズですが、完成後の見え方に直結する重要な工程なので、連携を密にして進めましょう。
STEP7|システム開発
Webサイトの裏側の仕組みを構築するのがシステム開発です。
WordPressなどのCMSを導入して編集しやすくしたり、商品管理や予約機能を組み込んだりと、目的に合わせて機能を整える工程です。見た目には表れにくい部分ですが、使いやすさや安定性に直結するため、丁寧な設計が求められるでしょう。
サーバーやドメインの設定、SSLの導入などもこのタイミングでします。要件定義で決めた内容に沿って開発が進められるか、コストや納期に収まるかも確認が必要です。
また、将来的にページを増やしたい場合や仕様変更の可能性がある場合は、メンテナンスしやすい構造にしておくことが後々の負担を減らすことにもつながります。
STEP8|テストの実施
公開前のテストでは、ページが正常に動くか、表示が崩れていないかをしっかり確認します。
誤字脱字やリンク切れ、フォームの動作不良など、小さなミスでもユーザーの信頼を損なう原因になるため、丁寧なチェックが必要です。スマートフォンやタブレットなど、複数の画面サイズやブラウザでも検証をして、見え方の違いにも対応しておきましょう。
事前に「どの環境でどこまで動作を保証するか」を決めておくと、テスト内容がブレにくくなります。テストと修正を何度か繰り返す前提で、スケジュールには余裕を持たせるのが理想です。
一度で完璧に仕上げようとせず、気になる点は小まめに洗い出すとよいでしょう。
STEP9|リリース
すべての確認が終わったら、いよいよWebサイトを公開します。
本番環境にデータを移行し、ドメインの接続をしたうえで、最終チェックを実施します。リリース当日は、表示崩れや機能エラーなどが起きてもすぐ対応できるよう、制作チームと連携を取っておくと安心です。
また、Googleアナリティクスなどのアクセス解析ツールが正しく動作しているかもこの時点で確認しましょう。集客目的のサイトなら、SNSやメルマガ、プレスリリースなどで積極的に周知することも重要です。
Webサイト公開はゴールではなく、スタートです。公開後も改善や更新を重ねれば、Webサイトは自社の活動を支えるツールとして育っていくでしょう。
Webサイト制作・リリース後の運用の流れ

最後に、Webサイト制作・リリース後の運用の流れを解説します。
- メンテナンスと更新
- サイト分析と改善
- SNS運用やWeb広告などの集客施策
それぞれ詳しく見ていきましょう。
メンテナンスと更新
Webサイトを安定して使える状態に保つためには、定期的なメンテナンスが欠かせません。
たとえば、サーバー・ドメイン・SSLの有効期限チェックや障害対応、CMSのバージョンアップなどがあります。また、古い情報を放置せず、内容を更新していくことも信頼性の維持につながるでしょう。
特にCMSは、セキュリティ強化のためにもこまめな更新が必要です。こうした日常的な対応を続けることで、ユーザーが安心して利用できる状態を維持しやすくなります。
サイト分析と改善
サイトを公開したら、アクセス状況やユーザーの動きを分析して、改善につなげるのが大切です。
Google AnalyticsやSearch Consoleを使えば、閲覧数や離脱率などのデータを確認できます。たとえば「お問い合わせが増えない」「特定のページで離脱が多い」などの課題があれば、A/Bテストや導線の見直しをすると改善のヒントになるでしょう。
数字をもとに小さな改善を繰り返せば、サイトの成果を少しずつ伸ばせます。
SNS運用やWeb広告などの集客施策
Webサイトに人を集めるには、SNSや広告などの外部施策との連携が効果的です。
SNSでの発信は、情報を届けたい層にリーチしやすく、継続的な関係づくりにも役立ちます。広告を使えば、狙ったターゲットに直接アプローチできるでしょう。
また、SEOやコンテンツ更新だけでは届かない層にも情報を届けられます。自社の状況に合った施策を選ぶには、目的や予算をふまえて戦略を立てるのがおすすめです。
必要に応じて、制作会社や広告運用の専門家に相談して進めるのもひとつの方法です。
Webサイトを制作する流れを理解して集客に役立てよう

本記事では、Webサイトを制作する際の基本的な流れや、リリース後の運用方法について解説してきました。
Webサイトは「作って終わり」ではなく、継続的な改善と集客施策が欠かせません。事前準備から設計・開発、公開後の運用までを理解すれば、効果的なWeb活用が可能になるでしょう。
【スムーズなWebサイト制作のためのポイント】
- 目的・ターゲット・予算を事前に明確にする
- 制作ステップごとの工程と役割を理解する
- 公開後の運用や集客も見据えて準備する
効率よく成果を出すためにも、本記事を参考にWeb制作を計画的に取り組みましょう。