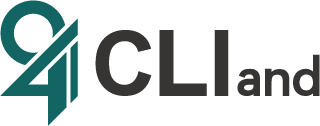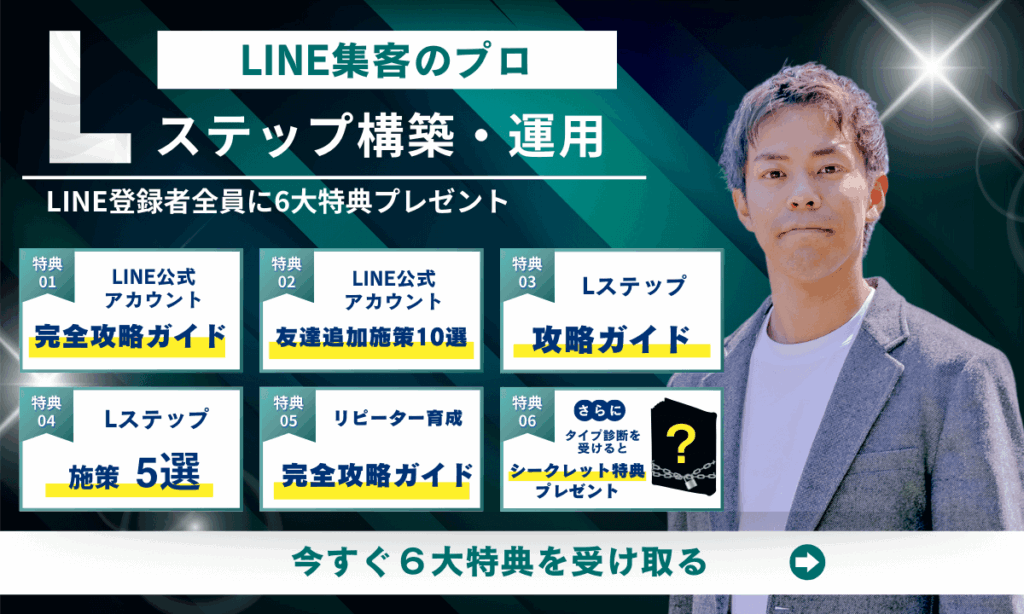Webサイトとホームページは似ていますが、意味や使い方の違いに迷う方も少なくありません。
「どちらの言葉を使うのが正しいのか知りたい」
「SEO的に有利な使い方を知りたい」
そこで今回は、Webサイトとホームページの違いを解説します。
Google検索での認識差や国内外の使い分け、関連用語との違いを紹介しています。
また、目的や相手に応じた適切な使い分け方法も解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
Webサイトとホームページは何が違う?

まず、Webサイトとホームページは何が違うか、以下の3つの視点で解説します。
- Webサイトとは
- ホームページとは
- Webサイトとホームページの違い
それぞれの用語が指す意味を整理し、正しく使い分けられるようにしましょう。
Webサイトとは
Webサイトとは、ブラウザで閲覧できる複数のWebページで構成された情報の集合体を指します。
これらのページは同一のドメイン内に配置され、リンクで相互接続されているため、訪問者がスムーズに各ページへ移動可能。ユーザー体験を意識した構成設計が前提となります。
会社案内やサービス内容・採用情報・ブログなど、テーマごとに異なるページを束ねたWebサイトが一般的です。この構成により、企業は多様な情報を効率的に発信し、目的別にユーザーを誘導できるでしょう。
Webサイトを運営するには、ドメイン(インターネット上の住所)とサーバー(情報を保存・配信する領域)が欠かせません。
種類としては、コーポレートサイト・ECサイト・オウンドメディア・ランディングページなどがあり、ビジネスモデルやマーケティング戦略に応じて最適な形態が選ばれます。
Webサイトの種類に関しては、以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

ホームページとは
ホームページには複数の意味があります。ここでは代表的な3つの使われ方を解説します。
- Webサイトのトップページ
- ブラウザで最初に表示されるページ
- Webサイト全般
それぞれの意味を正確に理解することで、文脈に応じた使い分けが可能になります。
Webサイトのトップページ
ホームページの1つ目の意味は、Webサイトのトップページです。トップページは訪問者が最初に到達する主要なページであり、Webサイト全体の印象を左右する起点でもあります。
ナビゲーションメニューの「ホーム」リンクやロゴをクリックすると、多くのWebサイトではこのトップページへ戻る設計になっているのはご存じでしょうか。
このページでは、企業概要や主要サービス、最新ニュースなどを簡潔にまとめ、閲覧者に対してサイト全体の方向性や価値を提示する役割を担います。
そのため、デザイン性・メッセージ性・視認性が特に重視され、ビジュアルやコピーにも戦略性が求められるでしょう。
ブラウザで最初に表示されるページ
2つ目の意味は、Webブラウザ起動時に表示されるスタートページです。Google ChromeやSafari、Microsoft Edgeなどでは、ユーザーが任意のページを初期表示に設定できます。
ニュースサイト・検索エンジン・自社の業務管理ツールなどをホームページに設定しておけば、業務効率や情報収集のスピードが向上するでしょう。
ただしこの意味でのホームページは、Webサイトそのものを指すわけではなく、ブラウザ機能の一部として用いられる表現である点を理解しておく必要があります。
Web制作やIT関連の文脈では、誤用を避けるためにも区別した方が適切でしょう。
Webサイト全般
3つ目は、日本で定着している「Webサイト全体」の意味です。インターネット黎明期に「ホームページを作る」という表現が広く使われた結果、ホームページ=Webサイトという認識が一般に浸透しました。
この言葉の使われ方は「意味の拡大化現象」とされ、多くの辞書でもトップページとWebサイトの両方の意味が記載されています。
特にテレビ、新聞、広告などでは「Webサイト」より「ホームページ」の方が馴染みがあり、非IT層に向けた表現として現在も多く使用されているのはご存じでしょうか。
また、Google検索トレンドを分析すると、「ホームページ」の検索数は「Webサイト」よりも高く、SEOキーワードとしても実用的に機能しています。
Webサイトとホームページの違い
Webサイトとホームページの違いは、構造と用途の観点から明確に区別できます。
Webサイトは、複数のWebページが組み合わさった情報の集合体です。一方、ホームページは、その中の1ページであるトップページ、または起点ページを指します。つまり、ホームページはWebサイトの一部です。
また、制作規模にも違いがあります。Webサイトはページ数が多く機能も複雑なため、制作費用は高額になりがちで、納期も長くなる傾向があるでしょう。
ホームページ(1ページ構成)は、会社概要や連絡先を載せる名刺代わりとして、低コストかつ短期間での制作が可能です。
制作会社に依頼する際、「ホームページを作りたい」と言えば1ページ、「Webサイトを作りたい」と言えば複数ページという解釈が一般的です。
そのため、Webに不慣れな相手には「ホームページ」専門家には「Webサイト」といったように、相手のリテラシーに応じて言葉を使い分けることで、認識のずれを避けてやり取りを円滑に進められるでしょう。
「Webサイト」と「ホームページ」を使い分ける5つのポイント

ここでは「Webサイト」と「ホームページ」を使い分けるポイントを5つ紹介します。
- Google検索における認識の違い
- 日本国内と海外における認識の違い
- 言葉の正確性で使い分ける
- SEO対策で使い分ける
- 相手に合わせて使い分ける
それぞれ詳しく見ていきましょう。
Google検索における認識の違い
Google検索では、「Webサイト」と「ホームページ」が一部では同義語として処理される傾向が見られます。
たとえば「Webサイト制作」と検索した場合でも、「ホームページ制作」が太字で強調される表示がなされるケースがあります。これはGoogleのアルゴリズムが日本語において両者の意味をほぼ同等と認識している可能性を示しているのです。
しかし、検索結果を比較すると「ホームページ制作」と「Webサイト制作」では、表示される内容に微細な違いが見られる場合があるのはご存じでしょうか。
この違いは、検索意図の解釈やキーワードごとのユーザー層の違いによるものです。そのため、SEO施策をする際は、表記ゆれだけでなく検索トレンドも考慮した上で、どちらの用語を使うべきかの判断が求められるでしょう。
日本国内と海外における認識の違い
日本では「ホームページ」という言葉が、インターネット黎明期からWebサイト全体を指す用語として広く使用されてきました。
その影響で、現在でもホームページ=Webサイトという認識が定着しています。多くの辞書でも「ホームページ」はトップページとWebサイトの両方の意味として掲載されています。
一方、英語圏では「homepage」はトップページ、またはブラウザのスタートページの意味に限定され、「Webサイト全体」を指す用語は「website」です。
このように言語的背景が異なるため、海外の関係者とやり取りする場合や英語で資料を作成する際は、「homepage」と「website」を正確に使い分けましょう。
海外進出やグローバル採用など、英語圏との接点がある企業では特に注意すべきポイントです。
言葉の正確性で使い分ける
定義に基づいて厳密に使い分けるならば、「Webサイト」は複数のWebページが集約された構造体であり、「ホームページ」はその中の特定のページを指す言葉です。
ホームページの具体例としては、Webサイトのトップページ、あるいはブラウザ起動時に表示されるスタートページが挙げられます。この違いは、Web制作の要件定義や設計フェーズで特に意識すべき点です。
企業がWeb制作会社へ依頼する際に「ホームページを作ってほしい」と伝えると、1ページ構成の簡易なサイトを想定される可能性があります。
一方「Webサイトを構築したい」と言えば、複数のページや機能を備えた構成と受け取られるのが一般的です。仕様の齟齬を防ぐためにも、用語を正確に使う習慣が求められるでしょう。
SEO対策で使い分ける
SEOの観点からは、「ホームページ」の方が「Webサイト」よりも検索需要が高く、検索トラフィックを狙うキーワードとしては有効です。
Googleトレンドでも「ホームページ」の検索ボリュームが上回っており、特に非IT層をターゲットにした集客施策では有利に働くでしょう。
そのため、SEO記事や広告文、サービス紹介ページにおいては、ユーザーの検索行動を踏まえ「ホームページ」の使用を優先するケースが多く見られます。
ただし、Web制作やマーケティングの専門家向けの場合は、「Webサイト」という用語の方が意味の正確性や専門性を伝えやすい表現となるでしょう。
キーワード選定においては、ターゲットの検索リテラシーと文脈の整合性を重視し、どちらの語句がユーザーの検索意図に一致するかを慎重に見極める必要があります。
相手に合わせて使い分ける
「Webサイト」と「ホームページ」を柔軟に使い分けるには、相手のITリテラシーや理解レベルを見極める姿勢が求められます。Web業界の関係者やシステム担当者に対しては、「Webサイト」と伝えることで、専門的な意図を正確に伝える効果があります。
一方、社内の非IT部門や顧客、年齢層が高い層に向けて説明する場合には、「ホームページ」と表現する方が言葉の意味が伝わりやすく、会話も円滑に進むでしょう。
実際に制作を外注する際、「ホームページを作ってほしい」と伝えれば1ページ構成、「Webサイトを構築したい」と言えば複数ページ構成と捉えられる傾向にあります。
このように、相手の前提知識を踏まえて適切な語句を選ぶことが、トラブル防止や効率的な進行に直結すると言ってもよいでしょう。
Webサイトやホームページと似ている言葉の意味と違い

最後に、Webサイトやホームページと似ている言葉の意味と違いを解説します。
- Web
- Webページ
- ブログ
- SNS
それぞれ詳しく見ていきましょう。
Web
Web(ウェブ)は「World Wide Web」の略で、インターネット上で情報を公開・共有・閲覧するための技術や仕組みの総称です。HTMLやURL、HTTPなどのプロトコルと技術が組み合わさることで、複数の情報が相互に接続され、リンクによって移動できる構造が構築されています。
私たちが日常的に利用しているWebサイトやWebページは、このWeb上に構築された個々の要素であり、情報を発信・受信するための手段として機能しています。
Webはそれ自体が一つのサービスではなく、Webサイト・SNS・EC・ブログなど多様な仕組みを動かすインフラとして、現代のインターネット環境に欠かせません。
そのため、Webサイトやページを理解する上で、基盤となるWebの概念や技術背景を把握することは、システム設計や制作時の理解を深めるためにも役立つでしょう。
Webページ
Webページとは、ブラウザで閲覧可能な1枚の文書ファイルを指します。HTMLで記述され、文章や画像、動画、リンク、フォームなどを組み合わせて構成されるページ単位の情報構造です。
たとえば、企業概要や採用情報、サービス紹介、商品説明、FAQ、問い合わせフォームなど、個別のテーマごとに1つのWebページが用意されているケースが一般的。ユーザーはこれらのページ間をリンクで移動しながら情報を取得します。
Webサイトとは、こうした複数のWebページが論理的に構成され、ドメインの下にまとめられた全体像を意味します。
ページごとの設計が情報の探しやすさやコンバージョンに影響するため、WebページはWebサイトにおける基本単位であり、情報設計・SEO・UI/UX戦略の出発点とも言えるでしょう。
ブログ
ブログは「Weblog(ウェブログ)」を語源とし、時系列で記事を更新・追加していく構造のWebサイト形式です。個人の発信ツールとして広まりましたが、現在は企業の情報発信、リード獲得、SEO対策を目的に導入されることが一般化しています。
企業がブログを運用するケースでは、自社サービスに関する知識や業界動向、活用事例など、読者の課題解決につながる内容を中心に継続的に配信。特にBtoB領域では、専門性を活かしたブログ記事が見込み顧客の獲得に直結するケースも多く、Webマーケティングの戦術の1つとして機能しています。
ブログはWebサイトの一部として構築されることが一般的ですが、情報の更新頻度と量が多いため、CMS(コンテンツ管理システム)による効率的な運用設計が欠かせません。
SNS
SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)は、ユーザー同士が交流・発信・情報共有をするためのオンラインサービスで、X(旧Twitter)やInstagram、Facebook、LinkedInなどが代表例といえるでしょう。
Webサイトとは異なるプラットフォームですが、企業のマーケティングや広報において、ユーザーとの接点を持つ手段として活用されるケースが増えています。
SNSを通じて企業が行う主な施策には、商品やサービスの認知向上、キャンペーンの周知、ターゲット層との継続的な対話、そしてWebサイトへの流入促進などがあります。特に、投稿内にリンクを設けて自社のランディングページやブログ記事に誘導する導線設計は、コンバージョン獲得にも有効です。
さらに、SNS広告とWebサイトを連携させることで、見込み顧客に対する再アプローチ(リターゲティング)も可能となり、戦略的なWeb集客における媒体として欠かせません。
Webサイトとホームページの違いを理解し、目的に合わせて正しく選んで活用しよう

本記事では、Webサイトとホームページの意味や違い、使い分けのポイントを解説してきました。
両者は混同されやすいですが、正しく理解すれば情報発信やSEO対策にも役立ちます。
【Webサイトとホームページを正しく使い分けるコツ】
- Google検索での認識差を押さえる
- 国内外の意味の違いを理解する
- 相手に合わせて言葉を選ぶ
用語を正確に使うことで、意図が明確に伝わり、信頼性や集客効果が高まります。ぜひ本記事を参考に、自社のWeb戦略に活用してみてください。