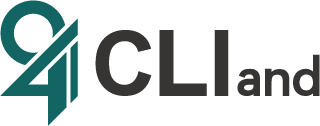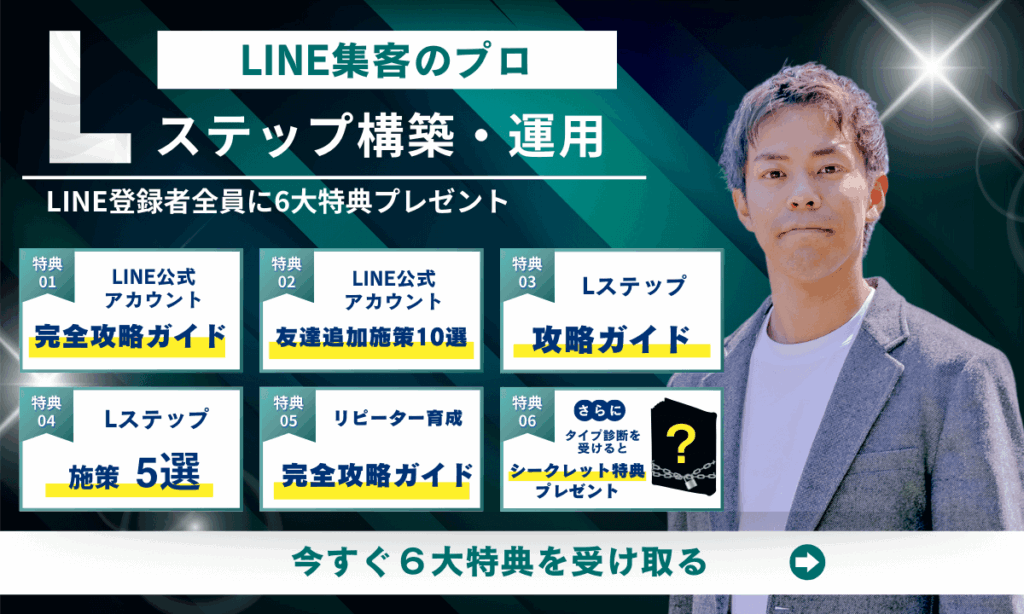Webサイトの企画書は制作を失敗させない土台ですが、以下の悩みで作成が止まる方も少なくありません。
「Webサイトの企画書には何を盛り込めばいいか分からない」
「Webサイトの企画書と提案書は何が違うか知りたい」
そこで今回は、Webサイト企画書の役割と作り方を解説します。
企画書と提案書の違い・6ステップの構成・期間と費用の見せ方に加え、ヒアリングや競合分析・見やすい資料化・効果的なオプション選定のコツも解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
Webサイトの企画書とは?必要な理由と提案書との違い

Webサイトの企画書は、目的・ターゲット・構成・予算・スケジュールを整理した制作指針です。プロジェクト開始前に企画を可視化することで、制作者と依頼者の認識をそろえ、成果につながる設計を具体化できます。
特に企業サイトでは、クライアントや社内決裁者が判断しやすい資料が求められ、内容の明確さや構成のわかりやすさが成果に直結します。制作会社が作成する場合、顧客の要件に対して、どのようなWeb構成や設計で応えるかを示す実行計画となるでしょう。
現状の課題とゴールを整理し、必要な制作手順を具体的に明記した資料があれば、方向性のブレや無駄な修正も防げます。
ここでは、Webサイト制作における企画書の意義と、提案書との違いを解説します。
Webサイト制作に企画書が必要な理由
Webサイトの企画書は、目的・ターゲット・構成・予算・スケジュールを整理し、成果につなげるために欠かせません。新規制作やリニューアル時には、事前の設計段階で施策を言語化し、関係者の認識をそろえる役割を担います。
具体的なゴール(例:販売促進・認知拡大・採用強化など)を設定したうえで、構成案やUI方針を明確にまとめましょう。企画書の完成度が低いと、ヒアリング内容が不十分になり、案件進行や成果物にズレが生じる原因となりかねません。
読み手に納得感を与えるには、根拠ある構成・数値・設計を盛り込み、見やすい構成で資料化するのがおすすめです。
Webサイトの企画書と提案書の違い
提案書は、課題に対して取りうる方向性やサービス内容を示す資料で、契約前の段階で活用されるケースが多いです。一方、企画書は、提案内容をもとに具体的な構成・設計・費用・スケジュールまで落とし込んだ実行計画です。
提案書=アイデア提示、企画書=実行指針という違いがあり、目的・活用タイミング・対象読者が異なります。企業によっては、社内用として企画書、顧客向けに提案書を使い分けるケースもあることを覚えておきましょう。
どちらも制作の意思決定を支える資料ですが、企画書は制作工程の全体像を示し、プロジェクト進行の軸となる点が特徴です。
【6ステップ】Webサイト制作における企画書の作り方

ここでは、Webサイト制作における企画書の作り方を紹介します。
- Webサイトの目的を明確にする
- ターゲット・ペルソナを設定する
- コンセプト・方向性を設定する
- コンテンツやデザインを紹介する
- Webサイト制作にかかる期間と費用を解説する
- 効果的なオプションを紹介する
それぞれ順番に見ていきましょう。
Webサイトの目的を明確にする
企画書にはWebサイトを制作する目的を具体的に記載する必要があります。新規立ち上げやリニューアルの背景には、解決したい課題や達成したい成果が明確に存在するはずです。
売上拡大・問い合わせ増加・認知向上など、事業に直結する目標をヒアリングに基づいて整理し、表面的な理由にとどめず経営目線での目的を定義することが求められるでしょう。
Webサイトは目的を実現する手段であり、戦略的な課題解決の一部として位置づけるのが説得力ある企画書につながります。
社内関係者と目的のすり合わせをして、全体の認識を統一しましょう。方向性のブレを防ぎ、制作後の運用体制にも好影響を及ぼすはずです。
ターゲット・ペルソナを設定する
誰に向けたWebサイトかを明示することが、コンテンツやデザインの方向性を決定する基準になります。
年齢や職業・居住地・行動傾向・悩みなど、具体的な情報をもとに詳細な人物像を設計しましょう。営業部門へのヒアリングを通じて、実在する見込み顧客のニーズを把握する作業も有効です。
ターゲットが曖昧なままだと制作全体がぶれやすくなり、広告効果やユーザー体験にも影響します。具体性と一貫性のあるペルソナ設定が、納得度の高い企画につながるでしょう。
既存顧客の購買データやアクセス解析ツールの活用も、信頼性の高いペルソナ設計に役立ちます。
コンセプト・方向性を設定する
ターゲットの属性やニーズに沿って、Webサイトのコンセプトと方向性を定めます。伝えたい価値や印象を簡潔にまとめ、サイト全体の軸となるメッセージや世界観を明文化しましょう。
ブランドイメージの一貫性を持たせるため、フォント・配色・トーン&マナーを統一させる設計が求められます。競合サイトとの違いを明確化するためにポジショニングマップを活用し、自社の強みを可視化するのも効果的。こうした設計により、制作工程での判断基準がぶれにくくなります。
ユーザーの目的や行動に応じて情報が自然に伝わるよう、ページ遷移や視線の動きも考慮した構成設計が欠かせません。
コンテンツやデザインを紹介する
企画書では、Webサイトに掲載する具体的なコンテンツやデザインイメージを視覚的に説明する必要があります。コンセプトに沿った構成で、ページの配置・配色・フォントなどを明示し、閲覧対象のユーザーにとって見やすく使いやすい設計であることを示しましょう。
高齢層向けなら大きな文字と操作性、若年層向けなら動画やビジュアルを活かした構成など、想定ユーザーに応じた工夫を記載。デザインカンプやワイヤーフレームを提示すれば、完成後のイメージが共有しやすくなります。
また、トップページと下層ページの役割を分けて説明すれば、構造の意図が明確になるでしょう。
Webサイト制作にかかる期間と費用を解説する
制作期間と費用は、企画書内で具体的な数値を示して説明する必要があります。要件定義からデザイン・実装・公開・保守までの工程を分けてスケジュールを記載し、各フェーズの工数を明示することで納期調整や社内稟議が通りやすくなります。
費用面では、初期制作費のほか、CMS利用料や運用保守、コンテンツ更新にかかる費用も含めて記載し、クライアントの検討を促しましょう。
料金が変動する可能性がある項目(追加ページ・写真撮影など)についても、事前に項目ごとに分けて見積もると認識のズレを防げるのでおすすめです。
効果的なオプションを紹介する
追加提案として、企画書に成果向上が見込めるオプションを盛り込めば、提案の価値を高められます。たとえば、SNS運用支援・ヒートマップ解析・SEO対策ツール・チャットボット設置・多言語対応などが挙げられます。
ターゲットや業種に応じて、必要性の高いものを選定して提案しましょう。提案内容の幅を広げれば、クライアントの課題を多角的に捉えた企画になります。
過去に成果を上げた実績や参考事例としての簡易な比較データを添えると、導入判断を後押しできるでしょう。
効果的なWebサイトの企画書を作成する5つのポイント

ここでは、効果的なWebサイトの企画書を作成するポイントを5つ紹介します。
- 丁寧にヒアリングする
- 競合分析を行う
- 見やすさ・わかりやすさを重視する
- ユーザー視点を意識する
- 状況に応じて見直し調整する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
丁寧にヒアリングする
企画書の精度は、クライアントからの情報収集に左右されます。初期段階で目的・背景・現状の課題を明確に把握しなければ、方向性が定まらず、成果につながる企画は設計できません。
ニーズや制約条件まで踏み込んで整理すれば、要件に合った施策を具体的に提案できる土台が整うでしょう。目標に向けたアプローチの形も示しやすくなり、企画書全体の説得力が高まります。
競合分析を行う
市場の動向や他社のWeb展開を把握すれば、自社の差別化ポイントを導き出せます。デザイン・導線設計・表現手法などの傾向を比較すれば、ターゲットに刺さる表現や構成の方向性の可視化が可能です。
競合分析の結果を元に戦略を立てれば、施策の妥当性に裏付けが生まれ、提案の説得力が増します。クライアントへの提示時も、感覚ではなく根拠に基づいた比較と提案ができるでしょう。
見やすさ・わかりやすさを重視する
読み手の理解を妨げない構成・デザインを意識するのが欠かせません。ページ構成やデザインの意図は、文章だけでなく図表・ワイヤーフレームを使って視覚的に提示します。
用語は一般的な表現に統一し、データや数値根拠を添えて論理的にまとめましょう。クライアントは企画書の質でWeb制作レベルを評価する場合もあるため、読みやすさ・整理された見た目は信頼につながります。
ユーザー視点を意識する
Webサイトの対象ユーザーとその行動や悩みを明確にすれば、訴求力のある提案が可能になります。ペルソナを設定し、そのユーザーが情報収集・比較・行動に至るまでの導線を設計する必要があります。
クライアントが伝えたい内容ではなく、閲覧者が知りたい情報を優先する構成が、滞在時間やCVRの向上につながるでしょう。ターゲットの心理に寄り添った設計は、結果としてクライアントの成果にも直結します。
状況に応じて見直し調整する
初稿で完成とは考えず、何度も精査・改善を繰り返す姿勢が求められます。コスト・リスクの記載漏れや、内容の一貫性の欠如は信頼を損なう要因になるといっても過言ではありません。
チェックリストやフィードバックを活用し、内容・構成・語句を修正しながら完成度を高めてください。目的や状況が変わった場合は、柔軟に対応できる構成にしておくことで、後工程での混乱も防げるでしょう。
Webサイトの企画・制作を外注するメリット

最後に、Webサイトの企画・制作を外注するメリットを3つ紹介します。
- 専門知識をもつプロに任せられる
- 制作時間を大幅に削減できる
- 客観的な視点を取り入れられる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
専門知識をもつプロに任せられる
Web制作を外注すれば、UI/UX設計・CMS導入・SEO対策などに精通した専門家に依頼できます。Web制作会社は、目的やターゲットをもとに構成・設計を体系的に組み立て、具体的な施策に落とし込む役割を担います。
要件整理から仕組みの実装までを一貫して行えるスキルセットにより、社内で不足しがちな領域を補完できるでしょう。成果につながる構成や導線設計を、専門知見に基づいて提案・実装できる点が外注の強みです。
制作時間を大幅に削減できる
外注により、要件定義・企画書作成・実装・改善までの全工程が効率化されます。制作会社は設計から運用までの進行に慣れているため、社内でゼロから進めるよりも圧倒的にスピードが出ます。
社内リソースを本業に集中させながら、公開までの時間を短縮できる点も魅力です。タスクごとの分担・スケジュール管理も外部が主導すれば、プロジェクトの長期化リスクを抑えられるでしょう。
客観的な視点を取り入れられる
外部パートナーは、内部にない客観性をもとにWebサイト全体を俯瞰して分析・提案できます。Googleアナリティクスなどの定量分析に加え、ヒアリングやアンケート調査などの定性情報も活用して、課題を可視化します。
自社視点では見えにくい構造上の問題や、ユーザー行動に基づく訴求軸の修正ポイントを提示できる点が強みです。トレンドや業界比較も踏まえた改善提案が可能になり、より成果につながるWeb設計が実現するでしょう。
Webサイトの企画書を作成して運営・集客を効率化させよう

本記事では、Webサイト企画書の必要性や作成手順、外注のメリットについて解説しました。
企画書は、目的・ペルソナ・構成を整理し、全体の方向性を共有するために欠かせません。構成が明確になれば、制作会社や社内メンバーとのやり取りもスムーズになります。
【効果的な企画書を作成するためのポイント】
- 目的やペルソナを明確にし、構成の軸を定める
- ユーザー視点で内容を整理し、見やすく仕上げる
- リソースに応じて外注も検討する
構成設計や施策の効果改善を図るには、専門的な視点からWebサイト企画書の設計が欠かせません。
要件整理やターゲット設計に不安がある場合は、Web制作会社に相談すれば、目的に合った構成や導線設計を具体化できるでしょう。
成果につながるWebサイト企画書をつくりたい方は、まずクライアンドへご相談ください。